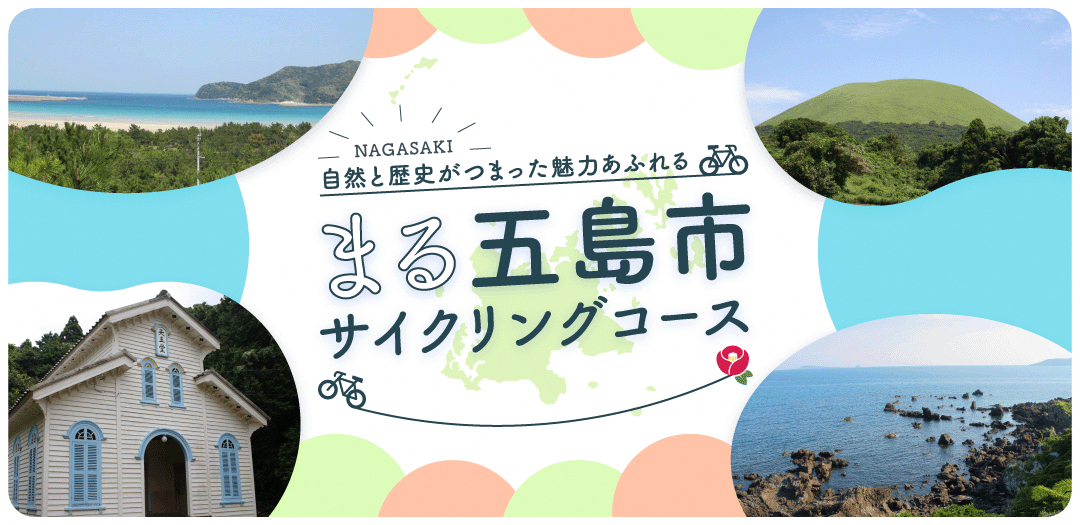五島ってこんなところ
九州最西端、五島列島の南西部に位置し、
コバルトブルーの海と白い砂浜、
四季を通して楽しめる釣りやマリンスポーツ、
キリシタンの歴史を物語る世界文化遺産
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」など
自然と歴史がつまった魅力あふれる島。
さあ、出かけてみよう!

Recommended content
おすすめのコンテンツ
Access Ranking
アクセス急上昇ランキング
Information
お知らせ
-
-
2024.
04.16 -
CHECKお知らせイベント
市制施行20周年記念 バラモン凧揚げ大会2024を開催します!
-
2024.
-
-
2024.
04.03 -
お知らせ
五島ワーケーション参加者の感想を追加しました!
-
2024.
-
-
2024.
03.28 -
お知らせ
It‘s almost spring! ~荒川温泉・五島沖鯨の骨のアーチ・山口酒屋・竈(かま)神社・カフェチルコロ~
-
2024.
-
-
2024.
03.26 -
お知らせ
五島列島・福江島「白亜の大瀬埼灯台まで歩いてみました!」~大瀬埼灯台完全ガイド~
-
2024.
-
-
2024.
03.25 -
お知らせ
カメラを持って五島列島(福江島)を旅する~歴史、伝統、文化を発見~
-
2024.
Movie